子供が小3で高校2年生相当の数検2級に合格しました。
この記事では勉強の仕方などをまとめます。
これまでの数検合格履歴
上の子が受けて合格したテストのまとめです。
| 学年 | 月 | 合格級 |
|---|---|---|
| 年中 | 10月 | 10級 |
| 年長 | 4月 | 9級 |
| 小1 | 4月 | 8級 |
| 6月 | 7級 | |
| 10月 | 6級 | |
| 小2 | 5月 | 4級 |
| 8月 | 5級※ | |
| 1月 | 準2級 | |
| 小3 | 9月 | 2級一次 |
| 3月 | 2級二次 |
※コロナで延期になったため4級と順番が逆転
主な勉強方法
計算は公文式で高1部分までやり、それ以外は僕が教えました。
準2級合格後、2級に向けて使った教材は、数検の市販の
- 要点整理
- 過去問
- 記述式演習帳
の3つです。
普段は中学受験塾のカリキュラムに乗って学習しているので、
数検は長期休みを活用して進めました。
1.要点整理
まずは数検公式本「数学検定2級要点整理」を使って各単元の内容を簡単に教え、基本問題と練習問題を中心に解きました。
基本問題は問題のすぐ下に答えがあるので、数分考えて分からなければ答えを見ます。
練習問題は答えが別冊ですが、解き方はほぼ同じ。
小3の夏休みに毎日30分から1時間くらいずつコツコツ進め、夏休みのうちにほぼ全範囲を終了しました。
力を入れたのは、方程式系、微積、三角関数など。ベクトル、数列、指数対数、数学的帰納法などは定着率が低かったと思います。
2.過去問
本番に向けて、こちらも数検公式本の「数検2級過去問」をやりました。全4回分収録。
最初は散々でしたが結果は徐々に上向き、4回目では一次試験は合格圏内、二次試験は記述の採点を厳しめにすると当落ギリギリよりやや下、という感じだったと思います。
要点整理でやった内容のうち、分かっていないものや忘れやすいものも分かったので、強化しました。準2級以前の内容で忘れているもの、知らないものも多かったです。
- Σ記号の和の公式
- 接線の方程式
- 点と直線の距離
- 方べきの定理
- 円に内接する四角形の向かい合う角の和は180
などなど・・・
1回目の受検で一次合格
9月に1回目の数検2級受検をしました。結果はコチラに書いた通り、一次合格となりました。

二次は5点中3点に届かず(詳細は上の記事)
ネットで調べ回ったところ、二次の平均点の推移はこんな感じ。
- 2020年7月 2.2点
- 2020年8月 2.5点
- 2021年4月 2.5点
- 2021年7月 2.4点
- 2021年9月 1.7点 ←
- 2022年2月 2.8点
- 2022年3月 2.8点
今見てもやはりこの回は難しぎたと思います。
(易しくても受かっていたかは分かりませんが)
3.記述式演習帳
小3の冬休みに数検2級の勉強を再開。
まずは前回もやった「要点整理」のうち、ベクトル、数列など苦手分野の基本問題と練習の重要マークをもう一度解きました。1~2日で1単元のペースだったと思います。
そしてその次に、「記述式練習帳」を始めました。
この記述式演習帳は、大雑把に分けると、1章(計算)、2章(問題)、3章(証明)という感じの構成になっています。
今回は限られた時間で対策するため、2章のみやりました。
記述式練習帳は例題と練習問題の最初の2問で解き方の方針が似ていることが多いので、1日の中でここを連続してやるのが良い感じでした。2日目にその次の実践問題。
例題の解説を見る時は、解き方だけでなく、「どう書くか」も意識しました。
しかし数検の二次試験では、5級(中1)から過程を書かせる問題が2問程度出始め、準2級(高1)からはほぼ全問で過程の記述が必須になります。そのため小学生にとって、準2級以降では問題の難度に加え「論述」が大きな壁となります。
2回目の受検で二次合格!
3月に2回目の数検2級の二次試験を受検。
今回は5点中4点を獲得し、無事合格となりました。
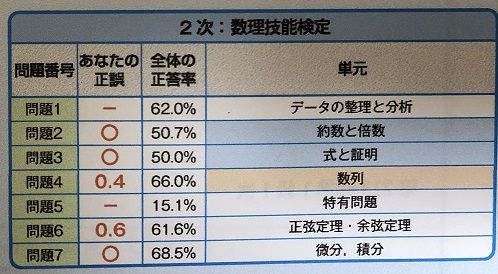
▲3問正解で3点と0.4+0.6で4点。
問題4と問題6は普通に間違えており、
記述の不足等による減点は無かった(と思われる)のが素晴らしいと思います。
低学年で数検を受ける方へのアドバイスはこちらにまとめました!
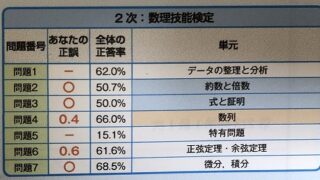

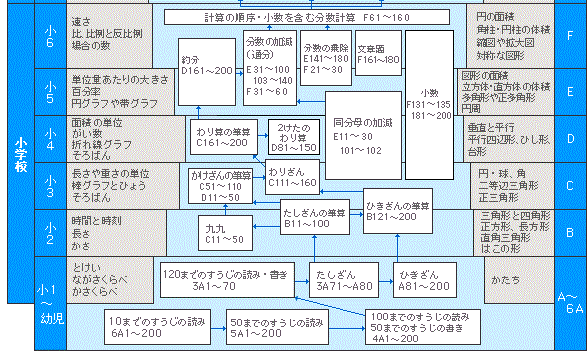
コメント